
私たちの身の回りには、スマートフォンや自動車、ビルや橋に至るまで、数多くの製品や構造物があふれています。これらの多くは「金属素材」なしには成り立たないと言っても過言ではありません。金属素材は、その種類の豊富さとそれぞれが持つユニークな特性により、あらゆる産業分野で基盤となる材料として活躍しています。 この記事では、そんな金属素材の種類について、基本的な分類から代表的な鉄鋼、多様な非鉄金属まで、それぞれの特徴や主な用途を網羅的に解説します。さらに、最適な材料を選ぶための重要なポイントもご紹介しますので、金属素材の知識を深め、より良いものづくりに繋げるための一助としてください。
H2:金属素材の基本!鉄鋼と非鉄金属とは?
金属素材は、私たちの生活や産業を支える上で欠かせない材料です。一言で金属と言っても、その種類は非常に多岐にわたりますが、大きく「鉄鋼(てっこう)」と「非鉄金属(ひてつきんぞく)」の2つに大別されます。この分類を理解することが、金属素材を知る第一歩となります。| 特徴項目 | 鉄鋼 | 非鉄金属 |
|---|---|---|
| 主成分 | 鉄 (Fe) | 鉄以外の金属(アルミニウム、銅、チタンなど多種多様) |
| 生産量・消費量 | 非常に多い | 鉄鋼に次ぐが、種類により大きく異なる |
| コスト | 一般的に安価なものが多い | 種類により高価なものもある |
| 代表的な特徴 | 高強度、加工性に優れる、磁性を持つものがある | 軽量、高耐食性、高導電性、高熱伝導性など多様 |
| 主な用途例 | 建築構造材、自動車ボディ、機械部品、工具 | 電線、サッシ、飲料缶、航空機部品、電子部品 |
鉄鋼とは?その特徴と利点
鉄鋼は、鉄(Fe)を主成分とし、通常0.02%から2.14%程度の炭素(C)を含む合金のことを指します。純粋な鉄は比較的柔らかく、そのままでは構造材料として十分な強度を持ちませんが、炭素を加えることで硬度や強度が著しく向上します。この炭素の含有量の調整や、さらに他の合金元素(マンガン、シリコン、クロム、ニッケルなど)を添加することで、非常に多様な性質を持つ鉄鋼材料が作られます。鉄鋼の大きな利点は、資源が豊富で比較的安価に入手できること、強度や靭性(ねばり強さ)といった機械的性質のバランスが良いこと、そして加工性や溶接性に優れているものが多く、様々な形状に成形しやすいことです。そのため、建築物、橋梁、自動車、鉄道、船舶、産業機械、家電製品など、社会のあらゆる場面で最も広く使用されている金属材料と言えるでしょう。
非鉄金属とは?その多様性と用途
非鉄金属とは、その名の通り鉄(Fe)以外のすべての金属元素およびそれらを主成分とする合金の総称です。アルミニウム(Al)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、鉛(Pb)、スズ(Sn)といった古くから利用されているものから、チタン(Ti)、マグネシウム(Mg)、ニッケル(Ni)などの比較的新しい工業材料、さらには金(Au)、銀(Ag)、白金(Pt)などの貴金属や、リチウム(Li)、レアアース(希土類元素)なども非鉄金属に含まれます。非鉄金属の種類は極めて多く、それぞれが鉄鋼にはない特有の優れた性質を持っています。例えば、アルミニウムは軽量性、銅は高い導電性と熱伝導性、チタンは高強度と優れた耐食性、ステンレス鋼(鉄鋼にも分類されるが、非鉄金属の特性も併せ持つ)は卓越した耐食性が特徴です。これらの特性を活かして、航空宇宙産業、エレクトロニクス、化学工業、医療分野など、鉄鋼だけでは対応できない様々な分野で重要な役割を担っています。
【鉄鋼編】代表的な金属素材の種類と特徴
鉄鋼は、添加される元素や熱処理の方法によって、その性質が大きく変化します。ここでは、工業製品や建築構造物などに広く利用される代表的な鉄鋼の種類について、それぞれの特徴と主な用途を詳しく見ていきましょう。| 種類 | 主なJIS記号例 | 特徴 | 主な用途例 |
|---|---|---|---|
| 炭素鋼 | S45C, SS400 | 炭素含有量で特性変化、加工性良好、比較的安価 | 機械部品、ボルト、ナット、建築構造材、橋梁 |
| 合金鋼 | SCM435, SNCM439 | 特定の元素添加で強度・靭性・耐熱性・耐食性などを向上 | 強力ボルト、歯車、シャフト、クランク軸、工具鋼 |
| 鋳鉄 | FC250, FCD450 | 炭素含有量高く鋳造性に優れる、振動減衰性良好 | マンホール蓋、水道管、エンジン部品、工作機械ベッド、ストーブ |
| ステンレス鋼(鉄鋼系) | SUS430, SUS410 | 主にクロムを含み耐食性を持つ(フェライト系、マルテンサイト系など一部) | 厨房用品、建築内装、自動車部品(排気系)、刃物 |
炭素鋼(S-C材、SS材など)の特徴と用途
炭素鋼は、鉄と炭素を主成分とする合金で、炭素の含有量によってその硬さや強度が大きく変わるのが特徴です。一般的に、炭素量が多いほど硬く強くなりますが、同時にもろくなる傾向があります。炭素鋼は加工がしやすく、比較的安価であるため、非常に広範囲な用途で使用されています。代表的なものには、S45C(機械構造用炭素鋼)やSS400(一般構造用圧延鋼材)などがあります。S45Cは、適度な強度と靭性を持ち、熱処理によってさらに特性を向上させることができるため、歯車やシャフト、ボルトなどの機械部品に用いられます。一方、SS400は、溶接性や加工性に優れており、建築物や橋梁の構造材、船舶の船体などに広く利用されています。
合金鋼(SCM材、SUS材の一部など)の特徴と用途
合金鋼は、炭素鋼に炭素以外の元素(合金元素)を1種類以上添加することで、特定の性質を向上させたり、新たな特性を持たせたりした鉄鋼です。添加される元素には、ニッケル(Ni)、クロム(Cr)、モリブデン(Mo)、マンガン(Mn)、バナジウム(V)などがあり、これらの組み合わせや添加量によって、強度、靭性、耐摩耗性、耐熱性、耐食性などが格段に高められます。例えば、クロムモリブデン鋼(SCM材)は、高い強度と靭性を兼ね備え、自動車のクランクシャフトや強力ボルトなどに使用されます。また、工具鋼なども合金鋼の一種で、高い硬度と耐摩耗性が求められる切削工具や金型などに用いられます。ステンレス鋼も広義には合金鋼に含まれ、特にマルテンサイト系ステンレス鋼(例:SUS410)などは、熱処理によって高い硬度が得られるため、刃物や一部の機械部品にも利用されます。
鋳鉄(FC材、FCD材など)の特徴と用途
鋳鉄は、炭素含有量が約2.14%を超える鉄と炭素の合金で、融点が比較的低く流動性が良いため、複雑な形状の製品を鋳造によって製造するのに適しています。鋳鉄の内部では、炭素の多くが黒鉛(グラファイト)として存在しており、この黒鉛の形状や分布によって鋳鉄の性質が大きく変わります。代表的な鋳鉄には、ねずみ鋳鉄(FC材)とダクタイル鋳鉄(FCD材)があります。ねずみ鋳鉄は、黒鉛が片状に分布しており、切削加工がしやすく、振動を吸収する能力(振動減衰能)に優れているため、工作機械のベッドやテーブル、マンホールの蓋、ストーブなどに用いられます。一方、ダクタイル鋳鉄は、黒鉛が球状に分布しているため、ねずみ鋳鉄よりも強度や延性(伸びやすさ)、靭性が大幅に向上しており、自動車のエンジン部品や足回り部品、水道管など、より高い強度が求められる部品に使用されます。
【非鉄金属編】多様な特性を持つ金属素材の種類
非鉄金属は、軽量性、耐食性、導電性、熱伝導性など、鉄鋼にはない優れた特性を持つものが多く、その種類も非常に豊富です。ここでは、私たちの生活や産業に深く関わっている代表的な非鉄金属の種類と、その特徴や用途について解説します。| 種類 | 主な特徴 | 主な用途例 |
|---|---|---|
| アルミニウム・合金 | 軽量、加工性・耐食性良好、リサイクル性高い | 航空機部品、自動車部品、サッシ、飲料缶、放熱フィン |
| 銅・合金 | 高い導電性・熱伝導性、加工性・耐食性・抗菌性良好 | 電線、電子部品、給水管、熱交換器、硬貨、調理器具 |
| ステンレス鋼(主として非鉄的特性) | 非常に優れた耐食性、多様な種類(SUS304, SUS316などオーステナイト系が代表) | 厨房設備、化学プラント、医療機器、食品設備、建築外装、時計 |
| チタン・合金 | 軽量・高強度、優れた耐食性・耐熱性、生体適合性良好 | 航空宇宙部品、化学装置、海水淡水化装置、医療用インプラント、ゴルフクラブ、メガネフレーム |
| マグネシウム合金 | 実用金属中最も軽量、比強度高い、振動吸収性良好 | ノートPC筐体、スマートフォン筐体、自動車部品(ステアリングホイール)、カメラボディ |
| 亜鉛・合金 | 融点低い、鋳造性・寸法精度良好、優れた耐食性(めっき用途) | ダイカスト製品(自動車部品、玩具)、鋼材の防食めっき(トタン)、乾電池外装 |
アルミニウム・アルミニウム合金の特徴と用途
アルミニウム(Al)は、軽量であることが最大の特徴で、その比重は鉄の約1/3です。この軽さに加えて、加工しやすく、塑性加工や鋳造、切削など様々な方法で成形できます。また、空気中で表面に緻密な酸化皮膜を自然に形成するため、優れた耐食性を示します。熱伝導性や電気伝導性も良好で、毒性がなくリサイクル性も高いことから、非常に幅広い分野で使用されています。純アルミニウムは柔らかいため、強度を高めるために銅、マグネシウム、ケイ素などの元素を添加したアルミニウム合金が広く用いられています。例えば、A5052合金は中程度の強度と良好な耐食性、加工性を持ち、板金部品や日用品に、A2017(ジュラルミン)は高い強度を持ち、航空機部品や構造材に使用されます。その他、建築用のサッシ、自動車のエンジン部品やホイール、飲料缶、調理器具、送電線など、その用途は枚挙にいとまがありません。
*関連ページ:アルミって「どこに」使われているの?(アルミの用途)
銅・銅合金(黄銅、青銅など)の特徴と用途
銅(Cu)は、銀に次いで高い電気伝導性と熱伝導性を持ち、その特性を活かして電線や電子部品、熱交換器のフィンなどに不可欠な金属素材です。加工性にも優れており、圧延、引抜き、鋳造などが容易で、様々な形状に加工できます。また、耐食性が良好で、特に海水に対する耐食性に優れるため、船舶部品や海水配管にも使用されます。銅合金としては、銅と亜鉛の合金である黄銅(真鍮)や、銅とスズの合金である青銅が代表的です。黄銅は、強度と展延性のバランスが良く、金色に近い美しい色調を持つため、装飾品、楽器(金管楽器)、バルブ、ボルト・ナットなどに使われます。青銅は、耐摩耗性や耐食性に優れ、軸受や歯車、ばね、美術工芸品などに用いられます。さらに、銅には抗菌性があることも知られており、ドアノブや手すりなど衛生面が重視される箇所での利用も進んでいます。
ステンレス鋼(SUS304、SUS316など)の特徴と用途
ステンレス鋼は、鉄を主成分としながら、クロム(Cr)を約10.5%以上含むことで、表面に非常に強固で安定した不動態皮膜を形成し、優れた耐食性(サビにくさ)を実現した合金鋼です。その特性から、非鉄金属的な側面も強く持っています。クロムの含有量や、ニッケル(Ni)、モリブデン(Mo)などの他の合金元素の添加によって、様々な種類のステンレス鋼が作られています。代表的なものに、SUS304(18Cr-8Ni)やSUS316(18Cr-12Ni-2.5Mo)などのオーステナイト系ステンレス鋼があります。これらは耐食性、加工性、溶接性に優れ、厨房設備、化学プラントのタンクや配管、医療機器、食品製造設備、建築物の内外装、家庭用品など、非常に広範囲で使用されています。その他、フェライト系ステンレス鋼(例:SUS430)は比較的安価で加工性に優れ、厨房用品や自動車の排気系部品に、マルテンサイト系ステンレス鋼(例:SUS410)は熱処理によって高い硬度が得られ、刃物や一部の機械部品に用いられます。
チタン・チタン合金の特徴と用途
チタン(Ti)は、軽量でありながら高い強度を持つ(比強度が高い)ことが最大の特徴です。その強度は炭素鋼に匹敵し、アルミニウムの約2倍の強度を持ちながら、密度は鉄の約60%程度です。また、海水をはじめとする多くの腐食環境に対して非常に優れた耐食性を示し、特に塩化物イオンに対する耐孔食性に優れています。耐熱性も比較的高く、生体適合性も良いため、人体に無害でアレルギー反応も起こしにくいという利点があります。これらの優れた特性から、航空機のエンジン部品や機体構造材、宇宙ロケット部品、化学プラントの反応容器や熱交換器、海水淡水化装置、発電所の復水器、医療用の人工骨やデンタルインプラント、さらにはゴルフクラブのヘッド、メガネフレーム、腕時計、カメラのボディなど、最先端技術分野から日用品まで幅広く利用されています。ただし、チタンは酸素や窒素と反応しやすく、高温での加工が難しいことや、材料自体のコストが高いことが課題とされることもあります。
マグネシウム合金の特徴と用途
マグネシウム(Mg)は、実用金属の中で最も軽い金属であり、その比重はアルミニウムの約2/3、鉄の約1/4です。この軽量性を活かして、製品の軽量化が強く求められる分野で注目されています。マグネシウム合金は、純マグネシウムにアルミニウム、亜鉛、マンガンなどを添加して強度や耐食性を改善したもので、比強度(単位重量あたりの強度)が高く、振動を吸収する能力(振動減衰能)や電磁波を遮蔽する能力にも優れています。また、切削加工性が非常に良いことも特徴の一つです。これらの特性から、ノートパソコンやスマートフォンの筐体、デジタルカメラのボディ、自動車のステアリングホイールやシートフレーム、航空機の部品、車椅子のフレームなど、軽量化による性能向上や携帯性向上が期待される製品に利用されています。しかし、マグネシウムは化学的に活性で燃えやすく、特に粉末状や薄板状では発火の危険性があるため取り扱いに注意が必要です。また、耐食性は他の金属に比べて劣るため、表面処理が必要となる場合が多いです。
亜鉛・亜鉛合金の特徴と用途
亜鉛(Zn)は、比較的融点が低く(約420℃)、溶融時の流動性が良いため、精密な鋳造に適しています。特に亜鉛合金ダイカストは、寸法精度が高く、薄肉で複雑な形状の製品を効率的に大量生産できるため、自動車のキャブレター部品やドアハンドル、電気機器の部品、建材部品、ファスナー、玩具などに広く利用されています。亜鉛のもう一つの重要な用途は、鉄鋼材料の防食(サビ止め)です。亜鉛は鉄よりもイオン化傾向が大きいため、鉄の表面に亜鉛をめっき(亜鉛めっき、トタンなど)すると、亜鉛が鉄よりも先に腐食することで鉄を保護する犠牲防食作用を示し、鉄鋼の寿命を大幅に延ばすことができます。このため、屋外で使用される鋼板やボルト・ナット、ガードレールなどに亜鉛めっきが施されています。また、亜鉛は乾電池の負極材料としても用いられています。

金属素材を選ぶ際の重要な5つのポイント
数ある金属素材の中から、目的や用途に最適なものを選ぶことは、製品の品質やコストを左右する重要なプロセスです。ここでは、金属素材を選定する際に特に考慮すべき5つのポイントを解説します。これらのポイントを押さえることで、より合理的で効果的な材料選択が可能になります。| 選定ポイント | 主な確認事項・考慮点 |
|---|---|
| 1. 強度と耐久性 | 引張強さ、降伏点、硬さ、靭性、耐疲労性、耐衝撃性、使用環境下でのクリープ特性など |
| 2. 加工性 | 切削性、プレス加工性、曲げ加工性、深絞り性、鋳造性、溶接性、熱処理の可否と効果など |
| 3. 耐食性・耐熱性 | 使用環境(温度、湿度、接触物質)での腐食速度、酸化性、耐熱温度、高温強度、熱膨張係数など |
| 4. コスト | 材料単価(重量あたり、体積あたり)、加工コスト、歩留まり、入手ロット、ライフサイクルコスト(メンテナンス含む) |
| 5. 入手性と供給安定性 | 市場での流通量、標準規格品の有無、納期、サプライヤーの信頼性、代替材料の有無など |
強度と耐久性(硬さ、引張強さ、耐疲労性など)を確認する
製品や部品がその役割を果たすためには、まず使用中に加わる力や環境に耐えうる強度と耐久性が必要です。具体的には、材料がどれくらいの力で変形し始めるか(降伏点)、どれくらいの力で破断するか(引張強さ)、表面がどれだけ傷つきにくいか(硬さ)、衝撃に対してどれだけ粘り強いか(靭性)、繰り返し荷重に対してどれだけ耐えられるか(耐疲労性)などを考慮します。例えば、大きな荷重がかかる構造部品には高い引張強さや降伏点を持つ材料が、頻繁に摩擦が生じる摺動部品には高い硬度や耐摩耗性を持つ材料が求められます。必要な強度・耐久性を明確にし、それを満たす金属素材を選定することが基本です。ただし、過剰な強度を持つ材料はコストが高くなりがちなので、要求される性能とコストのバランスを考えることも重要です。
加工性(切削性、鋳造性、溶接性など)を考慮する
選定した金属素材が、製品の形状や製造方法に適した加工性を持っているかどうかも重要なポイントです。加工性には、切削加工のしやすさ(切削性)、プレス加工や曲げ加工のしやすさ(塑性加工性)、溶かして型に流し込む際の扱いやすさ(鋳造性)、部材同士を接合する際の作業性(溶接性)などが含まれます。例えば、複雑な形状の部品を大量生産する場合は鋳造性の良い材料が、精密な加工が必要な場合は切削性の良い材料が適しています。加工性が悪い材料を選ぶと、加工時間が増加したり、特殊な工具や設備が必要になったりして、製造コストの上昇や生産効率の低下に繋がることがあります。そのため、設計段階からどのような加工方法を用いるかを想定し、それに適した金属素材を選ぶことが求められます。
*参考ページ:技術紹介・加工はとても便利 ~アルミ形材 45度切断~
耐食性・耐熱性(使用環境への適合性)を評価する
製品が使用される環境は様々であり、その環境に対する材料の耐性、特に耐食性と耐熱性は、製品の寿命や信頼性に大きく影響します。耐食性とは、水分、酸素、化学薬品などによる腐食(サビや変質)のしにくさのことです。屋外や湿度の高い場所、あるいは腐食性のガスや液体に触れるような環境で使用される部品には、高い耐食性を持つステンレス鋼やアルミニウム合金、チタンなどが選ばれます。一方、耐熱性は、高温環境下での強度維持能力や酸化しにくさを示します。エンジン部品やボイラー部品、工業炉の部材など、高温にさらされる用途では、耐熱性に優れた合金鋼やニッケル基合金、チタン合金などが検討されます。使用環境を正確に把握し、それに適合する耐食性・耐熱性を持つ材料を選ぶことが、製品の長期的な性能維持には不可欠です。
コスト(材料費、加工費、ライフサイクルコスト)を比較する
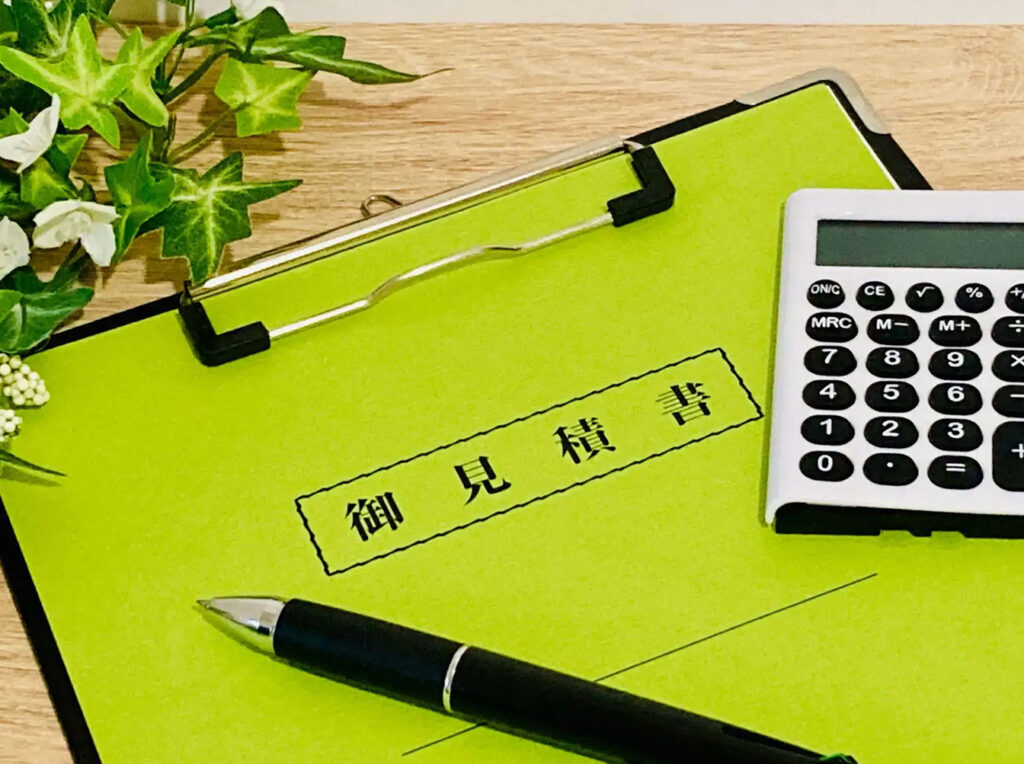
金属素材の選定において、コストは常に重要な検討項目です。材料自体の価格(材料費)はもちろんのこと、その材料を加工するためにかかる費用(加工費)も考慮に入れる必要があります。例えば、材料費が安くても加工が非常に難しい材料であれば、トータルの製造コストは高くなる可能性があります。さらに、製品の設計寿命やメンテナンスの頻度、廃棄時の処理費用なども含めたライフサイクルコスト(LCC)という視点も重要です。初期費用(イニシャルコスト)は高くても、耐久性が高くメンテナンスフリーであれば、長期的にはコストを抑えられる場合もあります。したがって、単に材料単価を比較するだけでなく、製造プロセス全体、さらには製品の使用期間全体を通じたトータルコストを評価し、最適なコストパフォーマンスを持つ材料を選定することが求められます。
入手性と供給安定性を確認する
どれほど優れた特性を持つ金属素材であっても、必要な時に必要な量を安定して調達できなければ、製品の生産計画に支障をきたす可能性があります。そのため、材料の入手性(Availability)と供給安定性は、選定における実務的な重要ポイントです。市場で一般的に流通している標準的な材料であれば入手は比較的容易ですが、特殊な合金や特定のメーカーしか製造していない材料の場合、納期が長くなったり、供給が不安定になったりするリスクがあります。また、国際情勢や資源価格の変動によって、特定の材料の価格が高騰したり、供給が途絶えたりすることも考慮に入れるべきです。したがって、材料選定の際には、複数の供給元を確保できるか、代替材料はあるか、将来的な供給見通しはどうか、といった点も確認しておくことが望ましいでしょう。
まとめ
この記事では、金属素材の基本的な分類である鉄鋼と非鉄金属から始まり、それぞれの代表的な種類、特徴、そして主な用途について解説してきました。 金属素材の世界は奥深く、多種多様な選択肢がありますが、それぞれの素材が持つ個性と能力を正しく理解することが、優れた製品開発や効率的な生産活動に繋がります。今回の情報が、皆様の金属素材選びの参考となり、より良いものづくりに貢献できれば大変うれしく思います。さらに詳しい金属素材の選定や加工、調達に関するご相談は、ニッカル商工のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが用途やご要望に応じた最適なご提案をいたします。
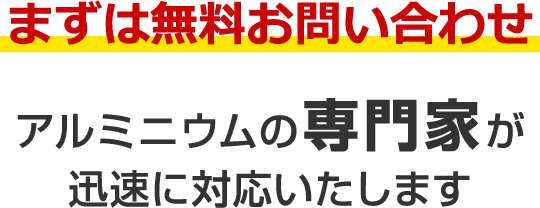
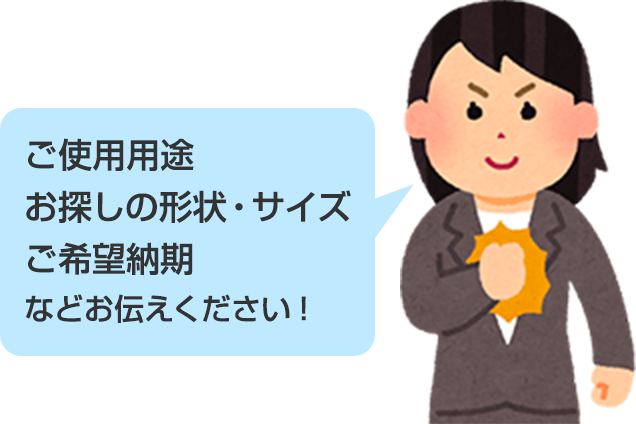
お電話でのお問い合わせ
 0120-163-256
0120-163-256
9:00~11:59 13:00~17:00(土日祝を除く)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ

